ベルデホ(Verdejo)はどんなブドウ品種?
スペイン・ルエダの白ワインを探しているあなたへ:爽やかで個性的な味わいとの出会い
ベルデホの特徴を知りたい方へ:アロマティックでフレッシュな品種の魅力を丁寧に解説
飲む前の基本情報:初めてベルデホを飲む方も、リピーターも産地と味の背景を再確認
この記事を読めば、スペインを代表する白ブドウ品種ベルデホの特徴や産地、味わいの魅力を1記事でしっかり理解できます。

概要
ベルデホ(Verdejo)は、スペイン北西部のルエダ(Rueda)を中心に栽培されている白ワイン用ブドウ品種です。スペインで最も重要な白ブドウのひとつであり、フレッシュでアロマティックな辛口白ワインの原料として高く評価されています。
その名の通り緑がかった果皮を持ち、柑橘類やハーブの香り、爽やかな酸、ほのかな苦味を伴う後味が特徴です。伝統的には酸化熟成されたスタイルが主流でしたが、近年では冷温管理されたステンレスタンクを用いたフレッシュなスタイルが主流となっています。ベルデホの品質と個性を最大限に引き出すため、早朝の手摘みによる収穫や低温での発酵が行われることが一般的です。
ルエダでは、原産地呼称制度(DO)によってベルデホが中心品種とされ、最低でも85%以上の使用が義務付けられた「ルエダ・ベルデホ」というラベル表記もあります。
 KSK
KSKソムリエ・ワインエキスパート試験対策としては、ルエダの特徴的な品種はベルデホとおぼえておけば大丈夫です!私はなかなかいい覚え方がなかったですが、必死に関連付けて覚えていました笑
名前の由来
「ベルデホ(Verdejo)」という名前は、スペイン語の「verde(緑)」に由来しており、その果皮の色合いにちなんで名付けられました。
この品種の起源については諸説ありますが、中世に北アフリカからスペインに伝わったとされる説や、ルエダ地方の土着品種として長い歴史を持つという説があります。いずれにしても、ベルデホは数百年にわたりスペインの乾燥した内陸地域で育まれ、今日の高品質ワインに進化してきました。



緑ワインとして有名なヴィーニョ・ヴェルデや、黒ブドウ品種のプティ・ヴェルドなどと同じ「緑色」の語源を持っていると考えると覚えやすいです。カタカナとして覚えるのではなく、現地の言語の意味を考えながら覚えると頭に残りやすいですよ!
栽培
ベルデホは暑く乾燥した気候に非常に適しており、スペイン内陸部のような昼夜の寒暖差が大きい地域に最適な品種です。糖度の上昇が早く、同時に酸も保ちやすいため、熟した果実味と爽やかな酸のバランスが取れたワインが生まれます。
- 萌芽(budding):やや早めです。
- 成熟(ripening):中庸〜早熟。8月下旬〜9月上旬に収穫されることが多いです。
- 樹勢(vigour):中程度で、管理しやすい品種です。
- 収量(yield):適度な収量。過剰に収量を上げると品質が落ちるため注意が必要です。
- 病害耐性:比較的病気に強く、特に乾燥地ではカビ系の病害が少ないです。
- 気候適性:高温乾燥に強く、灌漑の少ない環境でも育成可能。
ベルデホは酸化に対してやや弱い傾向があるため、収穫後は速やかに醸造所に運ばれ、低温での醸造が行われます。そのため、機械収穫ではなく夜間の手摘みにこだわる生産者も少なくありません。



スペイン内陸部は、雨も少なく、非常に乾燥した大陸性気候であり、とても埃っぽいです。ですが、ぶどうの栽培にとっては、非常に適した栽培を行うことができます!
味わい
ベルデホのワインは、香り高く、飲みやすく、食事にも合わせやすいことで人気を集めています。そのスタイルは生産者や醸造方法によって幅がありますが、一般的には以下のような特徴を持ちます。
- 色調:淡いレモンイエロー、若いうちは緑がかった輝き
- 香り:ライムやグレープフルーツ、白桃、メロン、ハーブ(フェンネルやアニス)、白い花
- 味わい:フレッシュでアロマティック。酸味がしっかりしており、口当たりはクリーン。後味にほのかな苦味を伴うのが特徴。
- 熟成スタイル:一部の高級ワインではオーク樽で発酵・熟成されることもあり、ナッツやバニラのニュアンスが加わります。
ベルデホは若飲みタイプが主流ですが、優れたワインは瓶内熟成にも耐え、数年の熟成でより複雑な味わいを見せてくれます。



内容だけ見ると、かなりソーヴィニョン・ブランに近い味わいの印象を受けますが、私の感覚だと、ソーヴィニョン・ブランの酸味やハーブのキリッとした感じよりは、若干ベルデホのほうが味わいが豊かといいますかリッチな印象を受けます。
主な生産地
スペイン
- ルエダ(Rueda DO)
ベルデホの本拠地であり、スペイン国内で最も多くベルデホが栽培されている地域です。標高700~800mの高地に位置し、昼夜の寒暖差が品質の高いブドウを育みます。ここでは、DOルエダとしてベルデホ主体のワインが多数生産されています。 - カスティーリャ・イ・レオン州全域
ルエダ以外でも、近隣地域でベルデホの栽培は盛んであり、Vino de la Tierra(地酒)として高品質なワインも見られます。
その他の地域
- アメリカ(カリフォルニア)
スペイン系移民の影響で一部地域でベルデホが導入されていますが、生産量は限定的です。 - オーストラリア
マイナー品種として一部のブティックワイナリーが注目し始めています。 - フランスやポルトガルでは、同名または類似名の品種が存在しますが、ベルデホとは異なるブドウである可能性が高く、混同には注意が必要です。



生産地域は限定的ですが、カリフォルニアやオーストラリアなどでも栽培しているとお聞きしたときは非常に驚きでした・・・。
代表的なシノニム
ベルデホはスペインを中心に栽培されてきたため、シノニムは比較的少ないですが、歴史的な記述や地域によって異なる呼び名が存在しています。
| シノニム名 | 名称の由来・背景 | 主な生産地 |
|---|---|---|
| Verdejo(ベルデホ) | スペイン語の「verde(緑)」に由来 | スペイン(ルエダ) |
| Verdeja(ベルデハ) | 古い呼び名、ルエダ地方の方言的表現 | スペイン(カスティーリャ地方) |
| Verdejo Blanco(ベルデホ・ブランコ) | 「白のベルデホ」を意味する。分類名として使われることもある | スペイン |



ヴェルデッロ(Verdello)という品種が、イタリアやポルトガルで示されることがありますが、別品種の場合が多いと言われています!
コラム
- 「酸化耐性に優れた果皮構造」
- ベルデホの果皮はポリフェノール濃度が高く、酸化防止機能が強いことで知られています。これは、19世紀の酸化的な熟成スタイル(アモンティリャード的)に適していた背景でもあり、現代においてもスキンコンタクトやシュール・リー製法に耐えうる潜在力を持ちます。
- 「ディアリルスルフィドとハーブ香の化学的関連性」
- ベルデホの典型的なアロマ(フェンネル、ハーブ、アニス)は、硫黄系揮発性化合物(VSCs)であるジメチルトリスルフィドやディアリルスルフィドに起因するケースがあります。これは過度の嫌気的醸造で増幅されやすく、還元香とのバランス管理が醸造の鍵となります。
- 「夜間収穫の先駆者的品種」
- 1980年代、ルエダ(Rueda DO)での品質向上のためにスペインで初めて本格的に夜間収穫が導入されたのがベルデホです。これは日中の高温による酸度低下と酸化を防ぐための処置であり、結果としてスペインにおける白ワイン品質革命の象徴となりました。
- 「クローン選抜と遺伝的多様性の課題」
- ベルデホは長年マッサルセレクション(選抜育種)主体で栽培されてきたため、クローンの多様性が乏しいとされます。現在スペインの研究機関(INIAなど)がクローン選抜を進めているものの、ローカル生態型(ecotypes)の同定が遅れており、収量・病害耐性の安定性に課題があります。
- 「プレ・フィロキセラ樹とルエダ・スーペリオール」
- ルエダではフィロキセラ以前に植えられた自根のベルデホ(特にサンティ・マルティン・デ・ルベアル地区)が現存しており、極めて低収量ながら深いミネラル感を持つワインが生まれます。このような区画からは「ルエダ・スーペリオール」等のサブゾーン指定が模索されており、スペイン白ワインのグラン・クリュ的価値が注目されています。



ワインのお供に、うんちくとして、ぜひともお話いただくとオモシロイと思っています笑
ルエダ・スーペリオールのサブゾーンが今後どうなっていくかは、ぜひ注目ですね!
おわりに



ほか、ブドウ品種についてまとめている関連記事もぜひご覧ください!
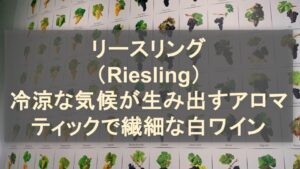
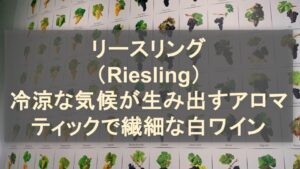
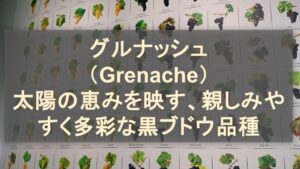
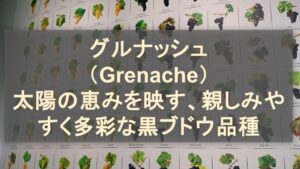
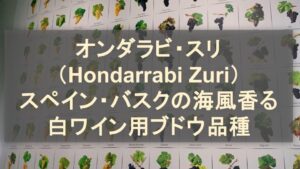
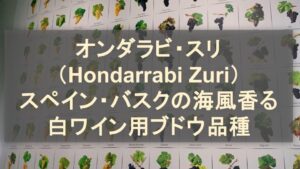
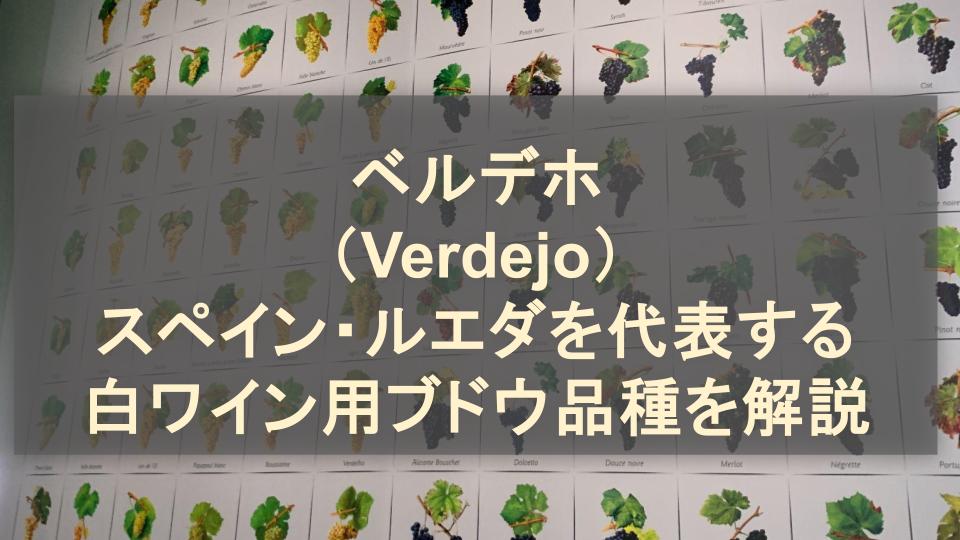
コメント